物流業界は今、大きな転換期を迎えています。
2024年問題として知られるこの課題に直面する中で、各社はどのような対策を講じるべきでしょうか。このシリーズ「5分でわかる『2024年問題とその対策」」では、2024年問題への様々な具体的な対策について解説します。
今回は現在の物流業界の現状と課題について詳しく解説します。
前回のおさらい
前回の第一回では2024年問題の背景と影響について解説しました。「働き方改革関連法」がこの問題の重要な背景といえます。この法律によって、時間外労働の上限規制、年次有給休暇の義務化、同一労働同一賃金、時間外労働に対する割増賃金の引き上げが改正されました。これによって、物流業界には大きく2つの影響がもたらされます。1つ目は、物流企業の売上・利益減少、2つ目にはトラックドライバーの収入減少です。これら2つは主に新たな法律によって時間外労働に上限が定められたことで引き起こされた影響です。
詳しくは、↓の記事をご覧ください。

物流業界の現状と課題
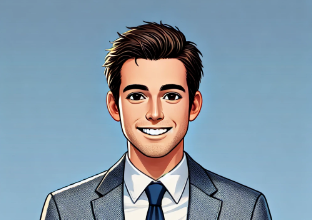 FC物流マガジン編集部
FC物流マガジン編集部まずは物流業界の現状を見てみましょう。
日夜、モノの移動で生活を支える物流・運送業界は業務の特性上、長時間労働が常態化しやすい業種でした。長時間労働の背景には、ドライバーの若手不足や高齢化、またEC(電子商取引)の成長による需要の増加などが挙げられます。特にECサイトの普及に伴う、宅配便の増加は顕著です。国土交通省の令和4年度宅配便等取扱実績関係資料によると令和4年度の宅配便取引個数は、50億588万個でした。これを前年度と単純比較すると、5265万個・対前年度比1.1%の増加です※1。運ぶ荷物が増加する中で、それを運ぶドライバーの人数は2021年時点でドライバー等輸送・機械運転従事者数は約84万人と、2012年から横ばいで推移しています。※2このように、物流業界は取り扱い荷物量が増加しているのにもかかわらず、ドライバーは増加しないという現状があります。
物流業界では荷主や元請運送事業者の立場が強いという現状もあります。この背景には特定の取引先に対する経営の依存度が高い運送業者が多いことが挙げられます。公正取引委員会によると運送事業者の41%は取引先数が10社以下です。さらに、取引高第1位の取引先に対して、39.7%もの運送事業者が売上の50%以上を依存し、62.8%の運送事業者が取引高第1位の取引先に30%以上を依存している現状があります。※3このような多くの運送事業者が少ない取引先に依存しているという構造が、荷主や元請運送事業者の立場を強めている。
物流業界では残業で稼ぐという考えも浸透しています。運送業では歩合制を採用している運送業者も多く、長時間労働も多いゆえに残業代を稼ぎやすいといえます。運送業者によっては固定残業代(みなし残業)を採用している会社もあります。しかし、運送業者のなかには固定残業代とは、残業の有無にかかわらず、一定時間の残業代を固定で支払う制度ですが、いくらでも残業させて良いと誤解している会社が目立ちます。
- ※1出典:国土交通省「令和4年度宅配便等取扱実績関係資料」
- ※2出典:公益社団法人全日本トラック協会「日本のトラック輸送産業 現状と課題2022」
- ※3出典:公正取引委員会「荷主と物流業者との取引に関する実態調査報告書(概要)」
物流業界の課題
物流業界が抱えている課題は、次の通りです。
- 人手不足
- 労働環境の悪化
- 再配達による負担
- 燃料費の高騰
- 2024年問題への対応
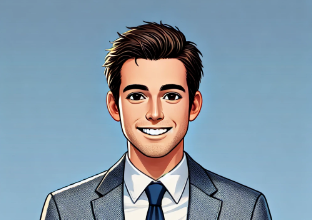 FC物流マガジン編集部
FC物流マガジン編集部それぞれの課題について見ていきましょう!

- 人手不足
-
物流業界の課題として、深刻な人手不足が挙げられます。
現在の物流業界では、需要の増加や労働力の減少により、タスク量に対して適切な労働者数を確保することが難しい状態です。
人手不足は業務の遅延や品質の低下につながり、業界全体の効率性に影響を与えるため、物流業界にとって大きな課題となっています。
とくに配送ドライバーの不足によって1人あたりのタスク量が超過しており、長時間労働や求人集客率の低下等、さまざまな弊害が生じています。
また、現在活躍している配送ドライバーの平均年齢が上がっているのも、見過ごせないリスクです。
人手不足を解消するために、物流業界では「労働環境の改善」や「業界全体のイメージ改革」をしなければなりません。
- 労働環境の悪化
-
物流業界では翌日配送や送料無料、指定日配達といった利用者にとって便利なサービスが普及していますが、その反面サービスを提供する側の労働環境が悪化しています。
翌日配送や送料無料によって受注数が増えて、労働者のタスク量が増加すれば、自然と物流業界は低コストで重労働をこなさなければなりません。
指定日配達により仕事終わりの夜遅くに利用者が荷物を受け取ると、配達員が仕事を終えるのは深夜近くになり、長時間労働・深夜労働が常態化してしまいます。
利用者が気軽に物流サービスを利用できる分、業界内の労働者が重労働をこなす必要性が生じて、労働環境が悪化していることが物流業界の課題です。
- 再配達による負担
-
再配達は物流業界における大きな負担です。
受取人の不在や住所の記載ミスにより商品の再配送が頻繁に発生し、労力・時間・コストを浪費しています。
利用者にとっては何度でも依頼できる再配達ですが、配送側からすると「再配達=無料で承っているサービス」なため、費用対効果が非常に悪いです。
再配達による負担を軽減するために、受け取り手続きの効率化や最適な配達ルートの確立等、再配達問題の解決策が求められています。
- 燃料費の高騰
-
物流業界には、燃料費の高騰という経済的な課題があります。
石油価格の上昇やエネルギーの需要と供給のバランス変動により、高騰する燃料費に物流業界は頭を悩ませています。
高騰する燃料費がコストの上昇につながり、業界全体の収益性を圧迫しているため大きな課題となっているのです。
持続可能な物流を実現するには、エネルギー効率の改善や代替エネルギーの導入、ルートの最適化等、燃料費の削減策が必要です。
2024年問題への対応
物流業界において「2024年問題」と呼ばれる課題が生じています。
2024年問題とは働き方改革によって2024年4月1日以降、ドライバーの時間外労働の上限規制(年960時間)が適応されることにより生じる課題です。
ドライバーの労働時間が規制されることにより、物流業界の売り上げやドライバーの収入が低下し、物流コストの増加が見込まれます。
さらに時間内に膨大な個数の荷物を配送しなければならないため、無理なタスク量が生じて業務の効率化やドライバーの採用等、さまざまな課題が生じます。
働き方改革により1人あたりの業務負担が軽減するかわりに、業界全体に大きな課題が生じる2024年問題へ、どのように対応するべきか対策を講じることが重要です。
トラックリースバックという選択
このような2024年問題の影響に対処していくために、車両をリースバックするという選択肢があります。使用している車両をリースバックすることで、資金調達、財務改善、CF(キャッシュフロー)改善に繋がります。弊社が手掛けるリースバックサービスである「FC車両リース」は、リース契約の満了時に車両の買い戻しができるオペレーティングリースという他社にない強みがあります
事例紹介:人材不足や燃料費の高騰に直面している会社がFC車両リースを活用しCFを改善した事例
北関東地方で運送業を営むB社が弊社の車両リースバックサービスを活用することで、キャッシュフローが改善した事例を紹介いたします。B社は、長年新車を5年リースで購入していました。しかし、昨今の人手不足に対応するためにドライバーの給与を改善したり、燃料の高騰などの影響で、月々の資金繰りが厳しくなっていました。そこでB社は弊社の「FC車両リース」をご利用いただきました。例えば、既にリース期間が3年経過しているトラックは「FC車両リース」を活用し、更に5年間のリース契約を結ぶことで、結果的に一台のトラックのリース期間を8年に引き延ばすことが可能です。B社は13台のトラックで「FC車両リース」をご利用いただき、毎月のリース料を100万円削減することができました。
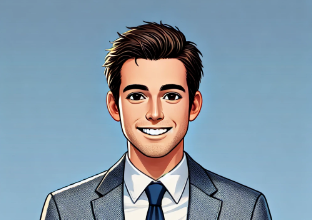 FC物流マガジン編集部
FC物流マガジン編集部このようにリース期間の引き延ばしにより月々のキャッシュフローの改善に繋がる「FC車両リース」は、変化に対応する運送会社様のお手伝いができます。
\「FC車両リース」の詳細はこちら/


まずはお気軽にお問い合わせください!
まずはお気軽に
お問い合わせください!
TEL 03-5212-5197
お見積もりの際は次の資料をご用意ください。
・決算書(直近3期分)
・車検証
・既存リース契約のわかるもの(契約書・お支払い明細の写し 等)
※お見積もり、審査は無料です。
提携企業さま、または直接弊社にお問い合わせください。

