8月1日から始まった臨時国会で、野党8党が共同提出した「ガソリン暫定税率廃止法案」が注目を集めています。 この法案が成立すれば、ガソリン価格に上乗せされていた1リッターあたり25.1円の暫定税率が11月1日から撤廃され、ガソリン代は大幅に値下がりする見込みです。ドライバーや企業にとって朗報となるこの動きですが、一方で大きな盲点も指摘されています。それは、物流の主役であるトラックなどディーゼル車が使用する軽油にかかる暫定税率が今回の法案に含まれていない点です。ガソリンだけ値下げされても、果たして物流コスト全体の削減につながるのでしょうか。本記事では、軽油暫定税率が除外された理由とその背景、そして物流業界や自治体への影響について専門的な視点から解説します。
ガソリン暫定税率廃止法案の概要と効果
野党共同提出のガソリン暫定税率廃止法案は、文字通りガソリン税に上乗せされている暫定税率部分(1リッター当たり25.1円)を撤廃しようというものです。政府与党がガソリン価格高騰対策として行ってきた補助金支給とは別に、税制そのものを見直す内容で、実現すればガソリン価格は現在より25円程度安くなる計算です。例えば7月下旬時点でレギュラーガソリンの全国平均価格が174円/L前後でしたが、これが約158.9円/Lまで下がる見通しとなります。ガソリン代の負担軽減は個人消費や企業の経費圧縮に直結し、景気下支えの効果も期待できます。
しかし、この法案には軽油に対する措置が含まれていません。トラックやバスなど物流・交通の現場で使われる軽油にも暫定税率(後述)が課されていますが、今回はその廃止が見送られました。その結果、ガソリンのみ値下げ、軽油は据え置きという形になり、燃料価格全体で見るとアンバランスが生じる恐れがあります。
軽油引取税が除外された理由 – 地方財源への配慮
軽油に課されている軽油引取税(いわゆる軽油税)が法案の対象から外れた背景には、地方財政への影響が大きく関わっています。軽油引取税は地方税であり、その税収は各都道府県など自治体の貴重な自主財源となっています。仮に軽油の暫定税率まで撤廃すると、自治体全体で年間約5000億円もの歳入減になると試算されます。この巨額な減収に対して明確な代替財源の示唆がないままでは、自治体が猛反発するのは避けられません。
実際、法案提出にあたって野党側も地方の反発を警戒し、軽油税は対象外とする判断を下したとされています。道路整備や公共交通支援など、地方インフラ維持に充てられている財源が急減すれば、地域の暮らしに支障が出かねません。こうした事情から、ガソリン暫定税率のみを先行して廃止し、軽油については今回は見送るという折衷策が取られたわけです。
軽油引取税の仕組みと“暫定”税率の実情
では、軽油引取税とはどのような税金なのでしょうか。その内訳を見てみましょう。
- 本則税率(法律で定められた基本税率):15円/リッター
- 暫定税率(特例税率):17.1円/リッター上乗せ
- 合計税額:32.1円/リッターあたり課税(本則15円 + 暫定17.1円)
軽油引取税には上記のように1リットルあたり32.1円もの税金がかかっており、その半分強が「暫定」と称する追加課税です。この暫定税率は今から約30年前、バブル崩壊後の財源不足の中で道路整備の財源確保を目的に導入されました。当初は期間限定の措置とされましたが、その後も延長が繰り返され、2009年に道路特定財源が一般財源化された後も課税は継続。いまや「暫定」の名とは裏腹に恒久的な税として定着しているのが実情です。
このように軽油税の暫定課税は長年維持されてきたため、地方自治体の歳入に深く組み込まれています。一方で、ガソリン側の暫定税廃止が現実味を帯びる中、失われる財源を将来どう補うのかという問題も浮上します。自動車関係団体(自動車総連など)からは「課税根拠を明確にした上で必要な税収規模を議論すべき」との提言も出ており、ガソリン・軽油双方の税制を包含した抜本的な見直しが求められている状況です。
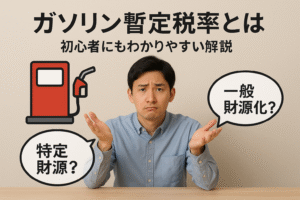
各方面の反応 – 物流業界と自治体の声
ガソリン暫定税率の廃止論議に対し、物流業界を中心に軽油税も含めた減税を求める声が強まっています。日本維新の会など一部野党は「物流コスト抑制のためにも軽油の暫定税率廃止は不可欠」と主張しており、地方への財政措置を講じた上で2026年度から軽油税も廃止する二段階減税案を提案しています。また国民民主党の玉木雄一郎代表も自身のX(旧Twitter)で「軽油の暫定税率廃止なしでは物流業界の負担は軽減されない。ガソリンとセットで見直すべき」と発信し、ガソリンと軽油両方の税率見直しを訴えました。
物流業界当事者からも切実な声が上がっています。日本トラック協会はかねてより軽油引取税の暫定税率廃止を政府に強く要望してきました。同協会は「物流の99%はトラック輸送に依存しており、軽油価格の負担軽減は物価対策そのもの」と訴えており、特に中小の運送業者にとって燃料費高騰は経営を直撃する重大な問題だと強調しています。現場のドライバーや経営者にとって、軽油のみ減税の恩恵が無い現状は大きな不公平感につながっていると言えるでしょう。
一方で、地方自治体からは強い反対の声が上がっています。軽油引取税は地方にとって重要な自主財源であり、特に地方部では道路の維持管理や地域の公共交通への補助金など生活インフラの運営に直結しています。ある県の財政担当者は「5000億円の減収は地方財政に深刻な影響を与える。代替財源が示されないまま廃止されれば、地域インフラの維持に支障をきたしかねない」と強い危機感を示しています。ガソリン税の暫定分廃止が物流業界にとって朗報である半面、自治体側にとっては財政基盤を揺るがす懸念となっているのです。
軽油だけ据え置きで価格差は僅差に…今後の影響は?
もし予定通り11月からガソリン暫定税率が撤廃され、軽油の税率がそのまま維持されれば、ガソリンと軽油の価格差は劇的に縮小することになります。試算では、7月28日時点の全国平均価格で比較するとレギュラーガソリン約174.0円/Lが158.9円/L前後に下がり、軽油は約154.1円/Lで据え置きです。その結果、両者の価格差は現在の約20円からわずか4円80銭程度へと縮まる見込みです。
従来、軽油がガソリンよりリッターあたり20円前後安いことは、ディーゼル車(特に商用車)を使うメリットの一つでした。ところが差が5円弱まで詰まると、その優位性はほぼ失われてしまいます。燃料費のアドバンテージがなくなれば、物流各社のコスト構造にも影響が及び、中長期的には運賃や物価への波及も懸念されます。さらに「軽油だけ減税されないのはおかしい」という不満が、物流会社だけでなくディーゼル乗用車のユーザーからも高まる可能性があります。実際、「ガソリンだけ安くなってもトラックやディーゼル車には関係ないじゃないか」といった声は既にSNS上でも散見されます。
政府・与党内でも、ガソリン税収の減少をどう補填するかや地方交付税措置の強化などが議論され始めています。軽油税の扱いについても、今回見送られただけで今後の大きな争点であり続けるでしょう。野党提案の二段階目の減税が実現するのか、あるいは自治体説得のための新たな財源策が示されるのか、予断を許さない状況です。物流コストと地域財政のバランスという難題にどう折り合いをつけるのか、関係者の動向から今後も目が離せません。

