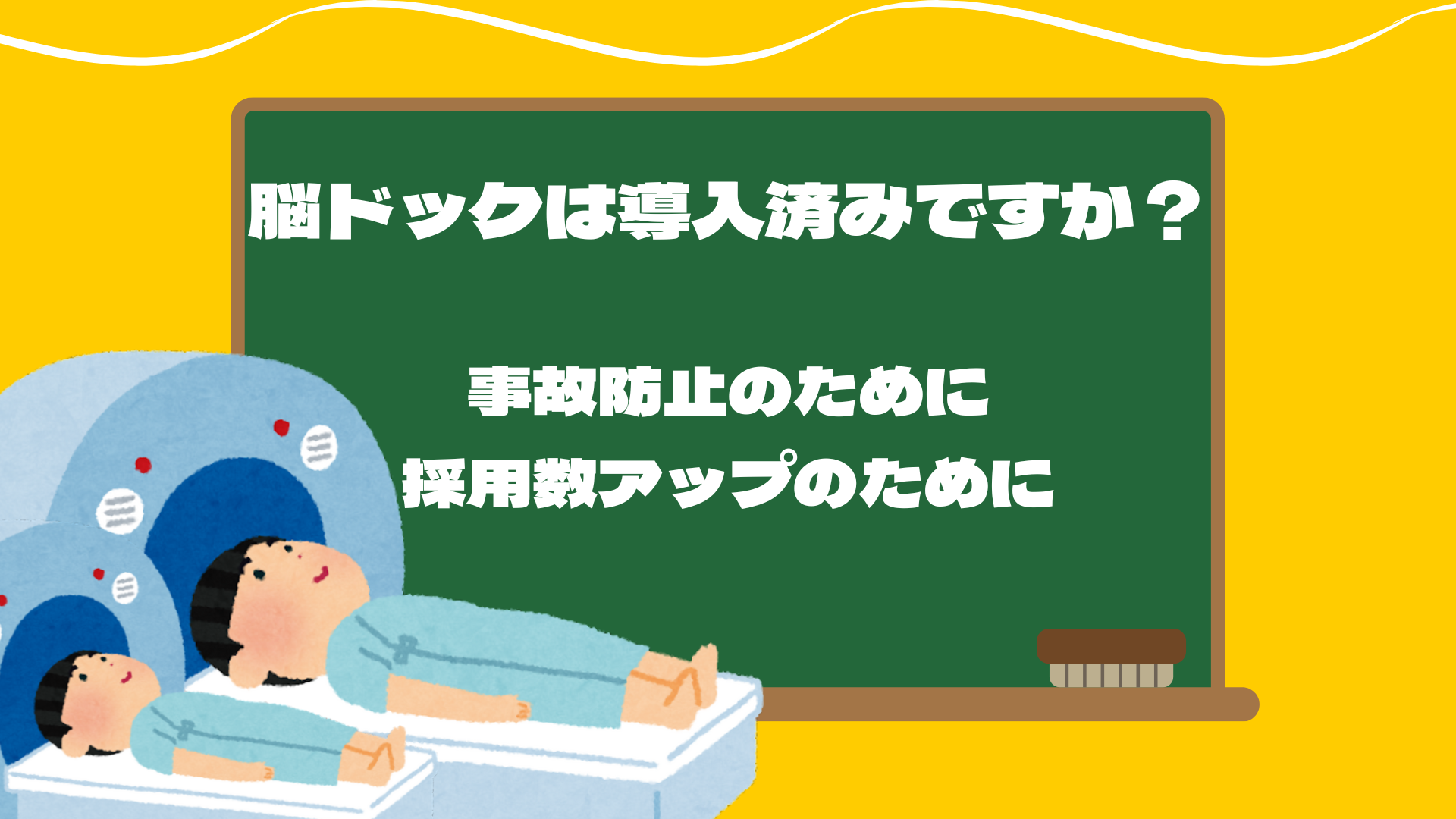物流と脳疾患
脳梗塞・脳出血・クモ膜下出血。これらの脳疾患の発症率は運送業がワ-スト1位となっている。ドライバーの高齢化が進む中、厚労省が発表している「過労死等の労災補償状況」の脳・心臓疾患に関する事案の労災請求件数は、過去10年以上にわたって運送業が最多となっている。この現実には多くの運送経営者も頭を悩ませているだろう。
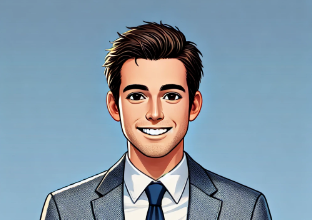 FC物流マガジン編集部
FC物流マガジン編集部
今回は脳疾患への対応について詳しく解説します。
問題点
この問題は運送業界全体で解決すべき問題として位置づけるべきだ。全日本トラック協会でも「自動車運送事業者における脳血管疾患対策ガイドライン~脳健診の必要性と活用~」について、というガイドラインも既に作られている。ガイドラインでは、自動車運送業者における脳健診の受診や治療の必要性について理解が浸透し、事業者による自主的なスクリーニング検査の導入を促進し、運転者の脳血管疾患による事故防止を図ることの重要性について触れている。
やはり、この問題の問題点はトラック運転手らの長時間労働が常態化していることが関係している。運送業界は2021年度には脳や心臓疾患で労災認定を受けた全労働者の3割を占めている。この背景には、食生活も深くかかわっている。運送業という性質上、食事をできる場所が限られている。そのため、手軽に食べることができる菓子パンやスナック菓子、ファーストフードなどの食べ物を食べることで、高血圧になりやすい。
厚生労働省によると、2021年度に国内では企業や官公庁などに雇用されている労働者は6013万人で、脳・心臓疾患での労災認定は172件あった。業種別の内訳で見ると、トラック運転手ら190万人が従事する「道路貨物運送業」が最多の56件で全体の32.5%を占めていた。比較できる09年度以降、この業種は常に最多となっている。
改善の取り組み
脳ドックを福利厚生に
こうした状況の中で、運送業界従事者の健康のために脳ドックの導入企業が増加している。運転事業者の脳MRI健診を支援している機関は、職業ドライバーに「脳MRI」の受診を推奨する。なぜなら、初期段階での発見が重要であるからだ。脳動脈瘤は進行すると開頭する必要があるが、初期であればカテーテル手術が可能で、術後2週間ほどで職場復帰できる場合が多い。
しかし実際には、金銭面な負担や時間面な制約のため脳ドックを気軽に受診できないドライバーも多い。そのため、脳ドックを気軽に受診してもらうために取り組みも行われている。金銭面な負担軽減のために日本全国のトラック協会で脳健診助成金を申請できる。また、一部の運送事業者では、金銭面と時間面のどちらの負担も軽減できるように従業員の脳MRI・MRIの自費診療にかかる費用を補助している場合もある。
脳ドックを受診することを事業所が援助するメリットはドライバーの健康と、運行上のリスクを軽減させられる2つのだけではない。家族の反対でドライバー業への就職を断念している求職者に対して、「ここの会社は脳ドックを受けさせてくれる」と言うことで家族の理解が得られやすいという、採用活動にもメリットがある。
国の方針
また、こうした状況を改善するため、厚労省はトラック運転手らの労働基準を定めた告示を改めた。2024年4月から適応される新基準では、月の拘束時間を9時間減の原則284時間とし、終業から次の始業までの間隔(勤務間インターバル)も延ばす。違反が確認されれば、国土交通省が事業者に対し、車両使用停止などの行政処分を行う。


\「FC車両リース」の詳細はこちら/


まずはお気軽にお問い合わせください!
まずはお気軽に
お問い合わせください!
TEL 03-5212-5197
お見積もりの際は次の資料をご用意ください。
・決算書(直近3期分)
・車検証
・既存リース契約のわかるもの(契約書・お支払い明細の写し 等)
※お見積もり、審査は無料です。
提携企業さま、または直接弊社にお問い合わせください。