FC車両リースについてのすべてを今すぐ知りたい方は下記の記事をクリック!↓

物流業界は今、大きな転換期を迎えています。
2024年問題として知られるこの課題に直面する中で、各社はどのような対策を講じるべきでしょうか。
このシリーズ「5分でわかる『2024年問題とその対策』」では、2024年問題への様々な具体的な対策について解説します。
今回の第一回では基本的な物流の2024年問題の概要、そして弊社のトラックリースバックについて詳しく解説します。
2024年問題とは?
2024年問題は、物流業界が直面する深刻な課題です。
これは、労働力不足やドライバーの高齢化、物流費の上昇などに起因しています。特に、労働時間規制の強化により、物流業界の運営が厳しくなることが予想されています。
2024年問題の背景と影響
2024年問題の背景:「働き方改革関連法」
日夜、モノの移動で生活を支える物流・運送業界は業務の特性上、長時間労働が常態化しやすい業種でした。
長時間労働の背景には、ドライバーの若手不足や高齢化、またEC(電子商取引)の成長による需要の増加などが挙げられます。
このような実態を改善すべく、働き方改革関連法に基づき、時間外労働時間の制限が定められました。
働き方改革法の主な改正内容
時間外労働の上限規制
働き方改革関連法施行により、今まで規制のなかった時間外労働に上限が設けられました。
法定労働時間は変わりませんが、時間外労働は「自動車運転業務は年960時間以上の労働は禁止」されています。
今までは労使が合意していれば、時間外労働時間に制限はありませんでしたが、2024年4月以降は罰則規定が追加され法的拘束力を持つようになった点も大きな変更点の1つです。
年次有給休暇取得の義務化
すべての企業が、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、最低年5日は有給を取得させることが義務付けられました。
この有給休暇は、正規雇用のみならず非正規雇用や場合によってはパートタイマーにも発生し、有給取得義務化の対象となります。
参照元:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf)
同一労働同一賃金
同一労働・同一賃金とは、正規雇用と非正規雇用の間での待遇格差をなくす取り組みです。
この取り組みは、主に以下の2つのルールを守る必要があります。
【同一労働・同一賃金】
正規雇用・非正規雇用の間で、基本給や賞与に差をつけない
求めがあった場合には、待遇差について理由を説明する
物流業界では非正規雇用のドライバーを採用している企業も多く、基準に則り評価することで、待遇差が発生しにくくなり労働者との紛争も防ぐ効果が期待できます。
時間外労働に対する割増賃金の引き上げ
2023年4月からは、60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられるのも大きな改正点の1つです。
大企業では変わらないものの、今まで猶予されていた中小企業の割増賃金率が25%から50%へと引き上げられます。
違反による罰則
2024年4月以降は、年間960時間以上の時間外労働が禁止され、今までにはなかった法的拘束力を持つことになります。万が一年間960時間を超えてしまうと、「30万円以下の罰金または6カ月以下の懲役」が経営者に科せられます。
参照元:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf)
2024年問題の2つの影響

物流企業の売上・利益減少
時間外労働時間の上限規制が設けられることで、ドライバーの労働時間が減り、会社全体の対応可能業務量も減少するため売上や利益が減少する恐れがあります。
特に物流業界は労働が売上に直結する労働集約型の産業であるため、上限規制によってダイレクトに影響を受けることとなるでしょう。
ドライバーの労働時間が減ることで、残業代を減らせるため、人件費のカットにつながるというメリットもありますが、オフィスの賃料や減価償却費といった固定費はそのままであるため、トータルで見ると企業にマイナスに影響する可能性が高いといえます。
トラックドライバーの収入減少
多くのドライバーが時間外労働を行っており、残業代によって一定の収入を確保している人も少なくありません。このような人たちの労働時間が減ると収入も減少し、生活に影響を及ぼす可能性があります。
場合によっては、より高い給料を提供する企業へ転職することも考えられます。
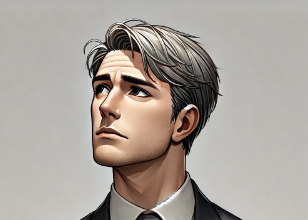 物流経営者さん
物流経営者さん資金面への影響が大きいけれど、すぐにできる対策はないの?
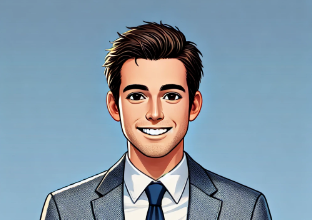 FC物流マガジン編集部
FC物流マガジン編集部あります!
「車両リースバック」なら現在使用している車両を使って資金調達が可能です。
車両のリースバックという選択
このような2024年問題の影響に対処していくために、車両をリースバックするという選択肢があります。
使用している車両をリースバックすることで、資金調達、財務改善、CF改善に繋がります。
弊社が手掛けるリースバックサービスである「FC車両リース」は、リース契約の満了時に車両の買い戻しができるオペレーティングリースという他社にない強みがあります。
\ 弊社の「FC車両リース」の詳細はこちら /
事例紹介:FC 車両リースを活用し2024年問題の対策を行った事例
運送会社A社様(関西エリア)が2024年問題に対応するために弊社のトラックリースバックを活用され、東海地方にある運送会社のM&Aを行った事例を紹介します。
A社様は2024年問題の規制前は1人のドライバーが関西から関東や東北への運送を担当していました。
しかし時間外労働の上限規制はこの運送を困難にしました。
そのため、輸送の中継地点を設けるために東海地方の運送会社を買収を検討されていました。
そこで、弊社の「FC車両リース」をご利用いただきました。
「FC車両ファンド」では一時的に車両の売却代金を受け取りながら、引き続きその車両をリースで使い続けることができます。
A社様は27台のトラックで「FC車両リース」をご利用いただき、6500万円の現金資金を調達することができました。
このように車両の価値を活かした新しい資金調達方法である「FC車両リース」は運送会社様の新しい一歩を踏み出すお手伝いができます。
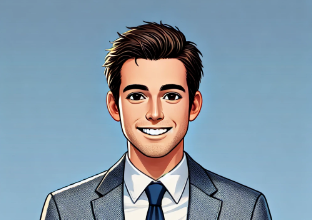 FC物流マガジン編集部
FC物流マガジン編集部以上、物流の2024年問題およびファンドクリエーショングループの「FC車両リース」のご紹介でした。



